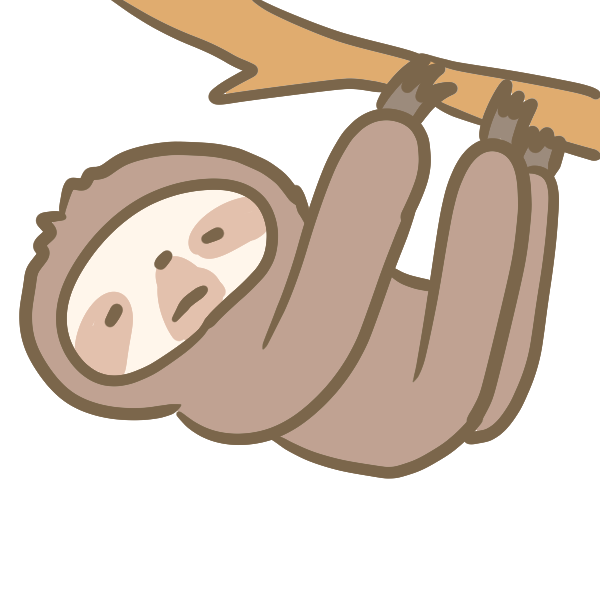
LPは改善するものと言われるけれど、どう改善したらいいかわからない……。

運用中の LP 改善は、新規制作とはまったく違った難しさだよね。
データを読み解き課題を1つずつ改善する LPO(ランディングページ最適化)を始めると、着実にCVと売上を伸ばせます。
逆にLPOの基本を知らず直感で動いてしまうと、本来拾えたはずの売上を取りこぼすかもしれません。
本記事では、業務委託で複数者のLPOを請け負っているマーケターチキンが、LPOの基本から具体的な実装手順まで解説します。
ヒートマップの見方からA/Bテスト設計、すぐ使える改善チェックリストまで手に入り、今日から自社サイトのCVRを底上げできるようまとめました!
CVRの伸び悩みを、ここで解決していきましょう。
LPOとは?コンバージョン率を高める最適化
LPO(ランディングページ最適化)とは、ユーザーの行動データを分析しながらランディングページを改善し、コンバージョン率を向上させるマーケティング手法です。

ランディングページ最適化 Landing Page Optimization の頭文字をとっており、エルピーオーと読みます。
LPOでは、広告やSEOからLPに集めた見込み客から、より多くの人が次のステップへと進む(CVする)ために改善を繰り返します。
そのため、ウェブ広告やEFO、SEOと組み合わせることで、総合的な成果向上が期待できます。
効果的なLPOを実施するには、主に3つのプロセスがあります。
- ユーザー行動の可視化:ヒートマップでクリック率やスクロール深度を計測します。
- 仮説検証:A/Bテストを活用し、デザインや文言の最適化を行います。
- 継続的な改善:定期的なデータ分析に基づき、改善サイクルを構築します。
キャッチコピーやCTAボタンを変えるだけで、ユーザーのクリック率が跳ね上がることもあります。
SEO・EFOとの違いを理解し戦略的に活用するポイント
LPO(ランディングページ最適化)と語感がよくにたマーケティング用語に、SEO・EFOがあります。
| 施策 | 言葉の意味 | 目的 |
|---|---|---|
| SEO | Search Engine Optimization検索エンジン最適化 | 検索上位表示による集客増 |
| EFO | Entry Form Optimization 入力フォーム最適化 | フォーム入力完了率向上 |
| LPO | Landing Page Optimization LP最適化 | ランディングページ全体のCVR向上 |

SEOは「集客」、EFOは「申し込み直前」、LPOは「ページ全体の最適化」を担います。
これらを組み合わせることで、検索からの流入を増やし(SEO)、ページ内での行動を促進し(LPO)、フォーム入力完了へと繋げる(EFO)と、ユーザージャーニー全体を最適化できます。
例えばECサイトの場合、SEOで商品ページへの流入を増やしつつ、LPOで商品画像の配置や価格表示を改善し、EFOで購入フォームを簡素化するなどが有効です。
サービス業ならSEOで比較記事を強化し、LPOで事例紹介動画を配置し、EFOで問い合わせフォームの項目数を最適化すると良いでしょう。
最適化の優先順位は業態によって異なります。リサーチ型のコンテンツが多いサイトはSEOとLPOの連携を、問い合わせフォームの離脱率が高いサイトはEFOとLPOの併用を優先すると効果的です。
データ分析で見えるユーザー心理的トリガー
データ分析を活用することで、ユーザーがランディングページでどのように行動し、どのような心理的なプロセスを経て意思決定しているかを可視化できます。

ユーザーの視線の動きや操作パターンから、心理を読み解いていきましょう。
- ページ25%に到達しない:ファーストビューに違和感があった
- CTAボタンが押されていない:ボタンに気づかなかった
- 長時間滞在したのに離脱した:情報が多すぎて迷ってしまった
ユーザー行動を計測するためには、分析ツールを使用します。
| 分析ツール | 把握できる心理的要素 |
|---|---|
| セッション記録 | ページ内での迷い行動・ためらいの瞬間 |
| スクロールマップ | コンテンツの優先順位と興味の減衰曲線 |
これらのデータを継続的に収集・分析し、ユーザーの心理的な抵抗を減らすようにページを改善していくことが、コンバージョン率向上の鍵となります。
実践で成功するLPO実装の5ステップ
LPOを効果的に実践するための5つのステップをご紹介します。
- 現状分析と明確なKPI設定で道筋を立てる
- ユーザー心理を捉えた改善仮説を組み立てる
- 効果検証、A/Bテストの設計
- ヒートマップで可視化する閲覧・クリック行動
- データを武器に改善サイクルを回し続ける
この5ステップを1サイクルとして実践すると、データに基づいた最適化が可能になり、LPのパフォーマンスを着実に向上させることができます。
各ステップにおける具体的な手法と実践のポイントを分かりやすく解説していきます。
ステップ1:現状分析と明確なKPI設定で道筋を立てる
LPOを成功させるための第一歩は、現状を客観的に把握することから始まります。
現在のランディングページのコンバージョン率や離脱率、ユーザーの平均滞在時間などの定量的なデータを収集し、課題を明確にしましょう。
- ファネルの各段階における離脱率資料請求画面到達率32%、申込完了率8%)
- デバイス別の行動傾向(モバイルでの離脱率がPCに比べて1.8倍高いなど)
- コンテンツの接触状況(動画再生完了率45%、PDFダウンロード率12%)
次に、改善目標となるKPIを「CTR15%向上」や「離脱率20%削減」のように、測定可能な数値で設定します。

特に重要なのは、最終目標(KGI)との整合性を確保することです!
例えば、ECサイトであれば「コンバージョン率2.5%」、リード獲得であれば「問い合わせ率1.8%」など、KGIから逆算された値を設定すると良いでしょう。
分析結果とKPIを照らし合わせ、優先度の高い改善ポイントから順に実施計画を作成します。
ステップ2:ユーザー心理を捉えた改善仮説を組み立てる
分析ツールでユーザー行動が可視化されたら、AIDMA(注意・関心・欲求・記憶・行動)やFOMO(取り残される恐怖)といった行動心理モデルも活用しながら、改善の仮説を立てます。
例えばファーストビューに「期間限定」と表示すると、FOMOを刺激し、即時行動を促せるかもしれません。
| 見えた行動 | 推定心理 | 改善仮説 |
|---|---|---|
| 55%位置で離脱急増 | ベネフィット不足で興味喪失 | FVを実績+期限付きオファー+CTAに強化 |
| 商品画像に誤クリック集中 | 詳細閲覧ニーズが満たされない | 画像カルーセル化&クリックでCTA強化 |
| 電話番号欄で離脱 30% | 個人情報提供への抵抗 | 電話番号任意化+安心コピー+1カラムに簡略化 |
仮説検証では、定量データと定性データを組み合わせて、ユーザーの真のニーズを見極めることが重要です。

ユーザーアンケートなどの定性的な情報も組み合わせながら、多角的に評価する仕組みを作りましょう。
ステップ3:効果検証、A/Bテストの設計
A/Bテストを効果的に実施するためには、3つの重要な設計要素を押さえる必要があります。
まず、テスト対象要素の選定では、ヘッドラインやCTAボタンなど、ユーザーの行動に直接影響する部分から優先的に選択します。
次に、テスト期間の決定には、想定される効果量に基づいて、統計的な有意性を担保できる計算式を用います。

ただし実情として、統計的優位性が担保できるほどの規模で検証できないケースもあります。
効果検証では、単に数値の大小を比較するだけでなく、統計的な有意性と実務的な有意性の両面から評価します。
最終的な判断は、ビジネス目標との整合性を常に意識し、データに基づいた意思決定プロセスを構築することが重要です。
ステップ4:ヒートマップで可視化する閲覧・クリック行動
ヒートマップ分析は、ユーザーの行動パターンを可視化する強力なツールです。
例えば、重要なCTAボタンがクリックされていない場合、配置やデザインの見直しが必要だと判断できます。
スクロールマップ分析では、ページのどの位置までスクロールされているかが明確になります。
特にスマホユーザーの場合、コンテンツをどこに配置するかが離脱率に大きく影響します。重要な情報が画面の下半分に隠れてしまっていないか確認しましょう。

誤タップが多発したり、目的のボタンが押しにくかったりと体験が悪化すると離脱されてしまいます!
- 視線追跡ヒートマップ:ユーザーの注目箇所を可視化、レイアウト改善に活用
- クリックヒートマップ:予想外のクリックが集中しているエリアからUIの問題点を発見
- スクロールヒートマップ:コンテンツの最適な配置と情報の優先順位を再構築
これらの分析結果をA/Bテストと組み合わせることで、定量的な改善効果の測定が可能になります。
ステップ5:データを武器に改善サイクルを回し続ける
データ分析に基づき継続的に改善サイクルを回すことが、LPO成功の鍵となります。
- 定例のデータレビュー会議でKPIの推移を共有し、改善施策の優先順位を決定
- テスト結果を部門を越えて共有し、広告運用や商品開発にも活用
- 定期的に市場動向を分析し、KPI目標値を見直す
特に効果的なのは、テスト結果を「仮説検証レポート」として蓄積し、組織のナレッジ資産とすることです。
これにより、新しいメンバーでも過去の事例を参照できるようになり、意思決定の精度が向上します。
長期的な効果測定では、コンバージョン率だけでなく「ページ滞在時間」や「スクロール深度」などの中間指標もモニタリングする必要があります。
季節的な要因や競合の動向も考慮し、柔軟な運用体制を構築しましょう。
即効性が高いLPO改善テクニック
LPO改善には、すぐに効果が出やすいテクニックがあります。
ここではその一部をご紹介します。
ファーストビューの最適化で滞在率を向上
ファーストビューの最適化は、ユーザーの滞在率を向上させるために非常に重要な施策です。
特に最初の3秒で「価値提案」「信頼性要素」「明確なCTA」の3点を伝えると、離脱率を大きく下げられます。
継続的な改善のためには、ヒートマップ分析とユーザー行動データを連携させることが効果的です。
月に一度デザインを刷新し、四半期ごとに根本的な見直しを組み合わせることで、持続的な効果を生み出すことができます。
クリック率を2倍にするCTAボタン設計
CTAボタンのクリック率を向上させるには、ユーザーがボタンを認識できるサイズや色味、心理的安全性を感じさせるマイクロコピーが大切です。

ボタンの色は、赤が緊急性を、緑はLINE登録を想起するなど、心理的な効果まで考慮しましょう。
適切な色彩を選択するだけでクリック率が上がることも珍しくありません。
- サイズ:誤タップを防ぎつつ、スマホでもタップしやすい大きさ
- 配置:スクロールせずに見えるファーストビューに収める
- 色味:ボタンだと気づけるよう、コンテンツと差をつけた色味
ボタンのテキストは、「申し込む」よりも「無料相談を予約する」のように、リスクを減らしてあげる文言を明確に表現すると効果的です。
矢印アイコンや人の視線、テキストの大きさなど視線を誘導するテクニックも活用しましょう。
必ずスマホでチェックする
今やパソコンユーザーよりもスマホユーザーの方が多いことは言うまでもありませんが、LPOに取り組む我々はパソコンを使う機会のほうが多いですよね。
そのため、LPOに関わる人物がパソコンユーザーからの見た目ばかり気にしてしまうことがあります。
BtoBの商材など一部を除き、スマホユーザーの方が多数ですから、スマホでのチェックは必ず実施しましょう。
LPの表示速度がコンバージョンに与える影響
LPの表示速度はコンバージョン率に直接影響を与えます。
いちユーザーとして、サイトがなかなか開けずイライラしたり、もはや開くのを諦めてしまった経験はだれにでもあるはずです。
せっかくLPを改善しているのに、ページ表示速度の遅さが原因で見られもしないなんてもったいないですよね。

外出先など、通信環境が不安定ななかページにアクセスしている可能性も考慮しましょう!
表示速度を改善するための具体的な対策として、以下の3つの手法が効果的です。
- 画像の最適化:WebP形式への変換と遅延読み込みの実装
- 不要なスクリプトの削除:使用していないCSS/JavaScriptを削除
- CDNの活用:静的なコンテンツを分散配信
単に数値を改善するだけでなく、実際のビジネス成果との関係を測定しながら最適化を進めることです。
まとめ
この記事では、LPOの基本的な概念から実践方法、データ分析による最適化手法まで幅広く解説しました。
ウェブサイトのランディングページを改善し、コンバージョン率を高めるLPOは、ビジネスの成長に欠かせない戦略です。
データに基づいた意思決定と継続的な改善サイクルを実践することで、効果的な顧客体験を創出し、売上アップを実現できます。

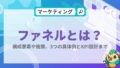

コメント